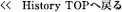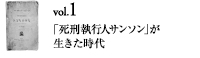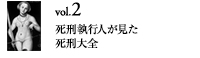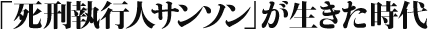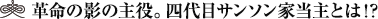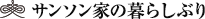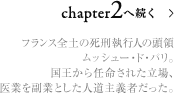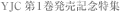


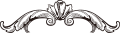
かつてパリにはほかの多くのヨーロッパの都市と同じように、世襲の死刑執行人がいた。パリの死刑執行人は「ムッシュー・ド・パリ」と呼ばれた。『死刑執行人サンソン』(集英社新書)は、六代にわたってムッシュー・ド・パリを務めたサンソン家の四代目当主、シャルル–アンリ・サンソンの半生を描いたものである。
世界の歴史において、死刑執行人の名前をだれが覚えていようか。シャルルもまた、ほかの多くの死刑執行人と同様に忘れ去られるはずだった。しかし、彼がムッシュー・ド・パリであったのは、フランス革命期のことであり、国王ルイ十六世と王妃マリー–アントワネットを処刑したのも彼なのであった。彼こそが革命の裏舞台を担った人物である。社会の片隅でひっそりと生きることを強いられてきた歴代当主の中で、シャルル–アンリは歴史の表舞台に躍り出、一時期はスター並みの扱いを受けたこともある。その数奇な運命を辿ろう。
フランス全土の死刑執行人の頭領である「ムッシュー・ド・パリ」。その職務を受け継いだサンソン家は三代目のジャン–バチストの頃まではかなり裕福だった。国王から委任された死刑執行人という職業により、二代目までは市場の商人から租税徴収する特権を持ち、かなりの財産を築き上げていた。特権廃止後は国から1万6000リーブルという高額の俸給や免税特権も与えられていたのである。
また、サンソン家では代々医業を副業にしてきた。つまり、人を死に至らしめることを職業としている人間が、もう一方では、人の命を長らえさせることもしていたのであった。これは一見奇妙に見えるかもしれないが、いろいろな刑を執行していた死刑執行人は、どこをどう叩けばどうなるか、どこが一番急所かといったことを体得し、人体の生理機能に詳しくなるのである。死体の引き取り手がない場合、埋葬までの間、死体の管理は死刑執行人に委ねられたが、それらの死体を解剖することによって、人体の構造を知悉するようにもなる。解剖室もちゃんとあった。歴代当主たちが解剖によって得た知識は、文書にしたためられて子孫に伝えられた。代々伝承された臨床医術により、普通の医者が匙を投げた病人やけが人を治癒させるなど、初代サンソン以来、評判は非常によかった。金持ちからは高額の報酬を受け取ったが、貧しい人たちからは一銭も受け取らなかった。医業は三代目の頃は年に6万リーヴルぐらいの収入があり、実入りの面でも大したものだが、サンソン家歴代当主たちにとって精神的にも大きな救いになっていた。公務とはいえ、そして、世の中のためだと自分自身を納得させようと努めていたとはいえ、人を殺めることに内心の嫌悪感を禁じ得なかったサンソン家の人々にとって、医業で人の命を救うのは何ものにも代えがたい慰めになっていたのである。
医業からの収入と国から支給される俸給を合わせると、三代目の頃は年に7万リーヴル(男子工場労働者の百倍に相当する年収)以上というかなりの高収入になるが、養うべき人間の数も多かった。まず、助手を始めとする雇い人が30人ぐらいはいただろうし、親戚筋の食客もいた。また、フランス全土の死刑執行人の筆頭に位置するムッシュー・ド・パリとして、住み込みで研修を受けにくる地方の死刑執行人の息子たちの面倒もみなければならなかった。
それでも、生活レベルはやはり貴族並みだった。サンソン家は二代目の頃から、パリ市北東の外れに広大な庭のある広い邸宅を構えた。1778年の三代目ジャン–バチストの死後、シャルル–アンリは遺産分割のため先祖代々の土地を手放さざるを得なくなるのだが、買い取った不動産開発業者のほうでは、そのままでは広すぎて商売にならないので、百十メートルと、六十メートルばかりの二本の道路を敷地内に新たに通さなければならなかったほどである。余暇も、やはり貴族と同様、狩猟で過ごすのが普通だった。

- サンソン家六代目アンリ-クレマン・サンソンによって、歴代当主の手記等を元に書かれた一族の歴史。『死刑執行人サンソン』の最も拠り所とする書物。

- パリ、モンマルトル墓地にあるサンソン家の墓。今でも、誰かが訪れ、花が捧げられていることも、しばしば見られる。

- 19世紀フランスを代表する作家バルザックはサンソン家と懇意だった。バルザック全集には彼の取材によるサンソン家のエピソードも書かれている。

- シャルルが描かれた肖像画はほとんど残っていない。これは20世紀初頭に挿絵画家により描かれたもの。「バルザック全集」に所収されている。