X上にて不定期で実施している「YJ作家トツゲキ質問箱」。ヤングジャンプの人気作家に匿名で直接質問できるこちらの企画。7月期は新人賞の審査員を務める田中一行先生への質問を募集し、お答え頂きました。
質問箱上で回答しているのですが、田中先生に作品への取り組み方・考え方を充実のボリュームでお答え頂きましたので、より多くの新人作家志望の方に見てもらいたいと思い、本インタビューページにもQ&A形式で掲載します! 特にラストの回答は全新人作家さん必見です!!
ゲーム展開や中身をどこまで事前に決めているか。
――ゲーム展開について質問なのですが、ルールと参加ギャンブラーが決まった時点で、勝敗や戦略の流れはどの程度まで決めていらっしゃいますか。
ゲーム中におけるキャラの苦悩や葛藤がすごく好きなのですが、 連載中にキャラクターが予想外の動きをしたり当初の予定と違う展開になったりすることもあるのでしょうか。
田中先生に性格が近いキャラクターは?
――『ジャンケットバンク』は個性豊かで魅力的なキャラクターが次々と登場します。キャラの中で、田中先生に性格や考え方が似ているキャラクターは誰ですか?
また、実際にいたら仲良くなれる、なりたいキャラクター、逆に仲良くなりたくない、なれないキャラクターも教えてほしいです!
考え方は各キャラクターに共感できる点はありますが、性格が似ているキャラはいないと思います。ただ、僕自身が漫画を描いていく中で壁にあたった際に編み出した「困難を乗り越えるための考え方」は、獅子神が成長する時に見せたものとほとんど同じです。
怖いのでほぼ全てのキャラクターと仲良くなりたくないですが、獅子神と黒光は友達になったら楽しそうだなと思います。
印象的なセリフ回しの秘訣
――「教育強度」「マッチポンプ慈悲」「謝罪風の音」と言ったこの作品でしか聞いたことのない秀逸な単語や、インパクトのあるセリフが数多く登場します。
このような印象的な言葉は、どのようにして生まれるのでしょうか。また、セリフを考える際に何か意識していることはありますか。
○○強度という言葉は普通に存在しますし、マッチポンプも慈悲も普通の言葉ですので、短文に関してはそれらをただ組み合わせただけです。読者の大多数がなんとなく意味はわかるけれど聞いたことはない、というように単語を組み合わせると印象深くなるような気がします。ただ言葉そのもののインパクトも大事ですが、同じくらい重要なのはその言葉にどのくらい共感、納得ができるかどうかだと思います。
「教育強度」はそれまでに瑚太郎がひたすら教育について暴論をぶちまけていたから意味が通じるのであって、突然教育強度なんて言われてもよくわかりませんし、マッチポンプ慈悲はそれまでの天堂の一連の行動を端的に表しているから「それな!」と印象に残るのであって、言葉だけでは作中に出てきた時ほどのインパクトはないと思います。
「謝罪風の音」も同じです。皆さんが一度は聞いたことがあるであろう意味のない言葉だけの謝罪を「音」という一言でまとめたので、共感が得られ、言葉が印象に残るんじゃないかと思っています。変な言葉を使うこと自体を目的にするのではなく、共感できる内容を変な言葉で言い換えることが大切だと思います。
セリフを考える際に意識していることは、「そのキャラが言わないことは言わない」ということと、「カッコよく言おうとしすぎて意味不明にならない」こと、「音読した時に語呂が良くなるようにする」ことです。
キャラクターとの距離感
――獅子神さんはいつも読者の気持ちを代弁してくれているような発言をしていますが、田中先生が漫画を描いている時は、獅子神さんサイドの心境、もしくはその時のギャンブラーの心境どちらに近い気持ちになっているのでしょうか。
メタ的な話で大変申し訳ないのですが、この漫画は一人の人間が頑張って考えているので描く際には全ての人物の心境になる必要があります。またそれを読んだ読者の皆さんの心境も推測する必要があるため、仮想読者も含めた人物全員に対して「何をわかっているか」「何がわかっていないか」「こういうことが起きたらどう思うか」というような感情と情報の仕分け作業をしながら描いていて、抜けや誤解がないように担当さんにチェックをしてもらっています。
ジャンケットバンクの読者は異様に読解力と理解度が高い方が多いですが、その人達を基準に合わせてしまうと難解過ぎて間口が狭くなってしまうので、僕は「ルールをよくわかっていない人」「数字を一切見ない人」を仮想読者の理解度に設定しています。何が起きているのかわからなくても、獅子神が「わかんね―ぞ!」と言ってくれると読んでいる人たちは「あ、獅子神もわかってないから自分もわからなくても今は大丈夫なんだ」と安心できるので、雰囲気で読んでも流れがわかりやすくなると思います。黎明風に言うと、「俺はアイツらを見てるお前を見てるよ」という感じです。
作中ゲームを考える手順
――どのようにして緻密なルールとその穴を作るのでしょうか。「ジャックポット・ジニー」での戦いでは、私はてっきり金貨の数を逆にするのかと思ったりしていたのですが予想は外れ、「金貨が実体化するには時間がかかる」という納得できる理由で勝利を収めていました。また、最近のデッドマンズキャンドルライトでは獅子神さんが蝋燭の火をつけまくって酸素を無くすという戦法を取りましたが、それはルールの「炎と共にタイマーのカウントは進んでいく」という前提があったからこそとれた戦法であり、読んでいた最中は炎と共にタイマーが進むことに疑問にすら感じていませんでした。少し思い返すだけでもルールの穴を突く戦法が上手く作られているのが分かってきます。ルール作りが上手いため現在のデビルズマイル・ツインズでもどうやって真経津さんが勝つのかワクワクが止まりません。この様に田中先生のルール作りは完璧だと思います。なのでどの様にしてルールを作っているのか教えていただけると嬉しいです。これからも頑張ってください。
ゲームのルールを作るためには、まずその戦いでもっともやりたいことを決める必要があります。例えば「敵が勝っているのに勝利まで辿り着けない」という勝ち方がカッコいいからやりたいと思いできたのが「ジャックポット・ジニー」で、これは勝ち方そのものがやりたいことでした。逆に「全てを正当に評価できるほど世界は完璧ではない」というテーマを描きたいと思い考えたのが「シヴァリング・ファイア」で、この場合は「世界が完璧ではない」という感覚的なことがやりたことだったので、それをゲーム上で表せる仕組みを考えました。どんなことがやりたいにせよ、まずは最終的な勝ち方を決めてからルールそのものを考えます。つまりルールを作ってから抜け穴を用意するのではなく、抜け穴を最初に考え、それに気づかれにくいようなルールを用意するという手順になります。
ゲームをどうやって考えるのかという質問はよく頂くのですが、実はこの「勝ち方」を決めるためにはその話のテーマと、敵となるキャラクターが必要不可欠なため、ゲームのみを単独で考えるということはほとんどしません。当たり前の話ですが、敵が三角なのか学なのかで、同じゲームを用意しても全く違う展開になるからです。
「シヴァリング・ファイア」を例に出すと、「世界が完璧ではない」というテーマ自体が、瑚太郎というキャラクターが持つ「教育」というテーマから派生して生まれています。「教育」というテーマを元に瑚太郎というキャラを考え、瑚太郎が持つ概念的な「弱点」がそのままゲームのテーマになり、かつそれが敗北する理由にもなると全体が非常にきれいに繋がります。なのでゲームを考える際はゲームだけを考えるのではなく、キャラクターと同時並行で調整していく必要があります。勝ち方が決まればあとはそれが理論上可能な仕組みを用意するだけなので、アイデアをたくさん出して整合性を取りながら要素を調整して行きます。
読者の目を引き、かつ愛されるキャラクターの作り方
――担当付の漫画家志望です。目を引くキャラクターを主人公にすると一般的な読者にウケず、かといって読者ウケを狙ったキャラクターはありきたりになってしまいます。先生はキャラクターの個性と、キャラクターの役割(主人公・脇役など)について、どのようにバランスを取っているか教えて下さい。
非常にリアルないい質問だと思います。僕も新人の時に全く同じ状態に陥りました。
まず質問に答えると、役割のない人物というのは物語に登場する必要がないと思っているので、どんなに小さなことでも全てのキャラクターには何かしらの役割をもたせます。「何もできないやつ」にも「何もできない」という役割が必要だという感じです。そしてその役割を与えた時に最も有効だと思う性質を考え、過剰に拡大解釈して個性の基礎にします。
主人公だからしっかり考えるとか、脇役だから適当でもいいということはなく、全員がその人物らしい個性を持つように考えます。神林さんが黎明よりキャラが薄いのは、彼がより一般人に近い感性を持っているからであり、適当に考えているからではありません。
ですがおそらくこの回答では今のあなたの問題にはあまり役に立たないと思いますので、何かしらの足しになることを願って、目を引くキャラクターについての注意点を補足します。
情報が少ないのでどういうズレがあるのかはあくまで推測ですが、おそらくあなたは「目を引く」ということを誤解しているように思います。質問の文章の行間を読むと、あなたが思う目を引くキャラクターというのは「独創性が強く、他では見たことのないキャラクター」という要素が強く含まれており、逆に読者ウケのいいキャラクターというものに「よく見るタイプの性格を持った、誰にでも理解できるキャラクター」という要素が入っているように感じます。
しかし非常に厳しい事実ですが、一般的な読者にウケていないと感じる時点でそのキャラクターはそもそも読者の目を引けていないか、目を引けてはいるけれど好かれていないかのどちらかだと思いますし、「読者ウケを狙ったありきたりなキャラクター」は実際には読者にウケてはいないはずなので、まずはそのズレを矯正するといいかと思います。
実際の人間で考えてみてください、好きな女性の気を引きたい2人の男がいたとして、一人は「おしゃれをして体を鍛え、楽しい会話をしながら好意を伝える」という行動を取ります。「目を引く」という点では実に意外性もなくありきたりな戦術ですが、彼が本当におしゃれで会話が面白いという実感が伴えば非常に魅力的な男性に映ると思います。
一方で、もう一人の男はもっと独創性のあるアピールをしようと「話したこともないのにラブレターを毎日100枚送り、好きな子そっくりの等身大の人形を常に抱いて歩く」という行動を取りました。「目を引く」という点では確かに後者の方が独創性があり注目を浴びると思いますが、最も重要な「相手から好かれるか?」という点ではほとんどの場合うまくいかないと思います。
つまり、「目を引く」という要素自体は印象がプラスでもマイナスでも成立してしまうため、「独創的=目を引く=好かれる」と誤解してしまうと奇抜な設定や奇行だけに頼るような悪目立ちするだけのキャラクターが生まれてしまい、肝心の「読者にウケる」という目的と乖離してしまうということです。特に残酷、残虐な表現は手軽に目を引ける一方で、匙加減を間違えるとキャラクターどころか作家自体に対し嫌悪感が湧いてしまうため、取り扱いには細心の注意が必要です。駅前で全裸になれば確かに人の目は引けますが好かれはしませんし、その全裸のおじさんに独自性を持たせようとしておしゃれなうさ耳をつけても嫌われることには変わりありません。
具体的な矯正方法としては、キャラクターの「特性」と「性質」を分けて考えることがおすすめです。
「特性」というのは「どら焼きが好きでネズミが嫌いで便利な道具を出す未来の猫型ロボット」といった設定面でのキャラクター性で、「性質」というのは「ちょっとドジでズボラで意外と口が悪いけど涙もろい人情家」というような人格、性格的な特徴を表します。
多くの漫画家志望者がこの「特性」の方を必死になって考え、特性によってキャラクターに独自性を出そうと頑張ります。それ自体はいいことなのですが、実際に自分の好きなキャラクターを思い出してみると、この特性はキャラクターを構成する非常に大きな要素ではあるものの、特性そのものが単独でその人物を好きな理由になることはあまり多くないと思います。「かめはめ波を撃てるサイヤ人だから」「体がゴムのように伸びるから」「伝説的なハンターの息子だから」という理由だけでそれぞれのキャラクターが好きな人は多くないと思います。もしこれだけでみんなに好かれるキャラクターが生まれるのならば、「かめはめ波(のようなもの)を撃てるサイヤ人(のようなもの)」という設定さえつければどんなキャラクターでも好かれることになってしまいますし、体がゴムのように伸びる凡人を描いても必ず大ヒットするはずです。
重要なのは、こうやって羅列しただけでどれが誰のことを言っているのかわかるというのが「特性」の持つ役割の一つであり、多くの人にその人物を紹介し興味を持ってもらう入口として非常に有効だという点です。
それに対し、「性質」というのはそのキャラクターの内面的な性格や行動理念を表すので、多くの人はキャラクターが持つ性質が「好きである理由」になることが多いです。
「困難に立ち向かい強敵に打ち勝つ仲間思いの熱い男」という性質を聞いて、これが誰のことを表しているかわかるでしょうか? おそらく特性の時とは違い、聞いた人によって誰のことを思い浮かべるかが変わると思いますが、頭に浮かんだキャラクターは「いいキャラクター」なはずです。つまり、いいキャラクターが持つ性質というものは、特性とは違い一言で済ませてしまおうとするとそれ自体は非常に「ありきたり」なものが多いということです。上に挙げた「熱い男」なんてこの世に何百何千と同じ性質を持ったキャラクターがいます。なぜかと言うとみんな熱い男が好きだからです。
だからこそ、自分が持つ独自性はここで最大限に発揮する必要があります。このみんなが好きな「ありきたり」を一言でまとめず、独自の目線で自分が思う最高の「一言でいうとありきたりだけど誰とも違う独創的なキャラクター」を探し、それを活かせる特性と組み合わせてください。「IQ500」という特性だけをキャラクターにをつけても、読者に「コイツ天才じゃん!」と実感させる「賢い」という性質は得られません。「賢い」というような実にありきたりな性質を、読者の目を引き、かつ愛されるキャラクターに持たせるためにこそ、作者の独創性を使ってください。それが上手く行った時に、読者はそのキャラクターを「このキャラは超かっこいいIQ500の天才なんだ!」と誰かに紹介してくれるはずです。
8月期審査員は、『BUNGO―ブンゴ―』の二宮裕次先生が登場!

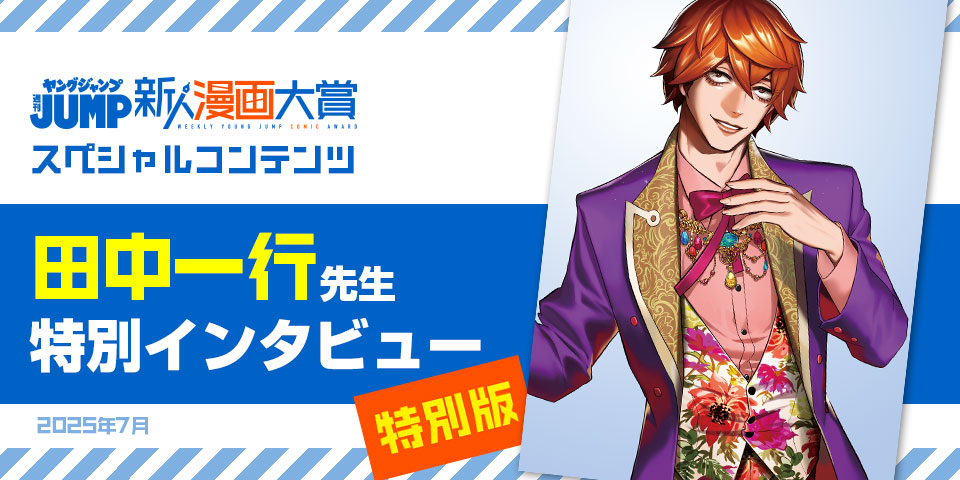

物語の中でルール説明が行われているタイミングで、決着までの全ての要素が決定しています。具体的には決着の方法、全ラウンドのスコアと各ラウンドで表したいテーマ、またその戦略をキャラクターが選択する理由、優勢劣勢の移り変わり、読者に伝えたい情報を開示するタイミングなどをルール説明時点までに決めています。数字上の展開は一切変更が効かないため、唯一予定外のことが起こる可能性がある点はキャラクターの心情、発言に関する部分です。
基本的に登場人物全員が異常者なので、僕が予測していたこととは全く違うことを感じ、その回を描くまで考えてもいなかった一面が見えることもあります。例としては、ピーキーピッグパレスでの村雨が患者や兄との関係を省みる展開は、直前まで全く予定にありませんでした。